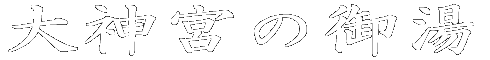
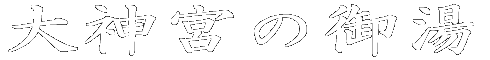
禰宜と氏子総代にて順の舞(三人舞)を舞った後に、神子も加わり湯立のう たぐらをうたう。
鈴を鳴らしながら足を軽く踏み変えながらうらぐらをうたう。
うたぐらの途中、「千早振る…、大社が森で…」とうたうときには湯木を平らにもった後、湯木で釜の湯をかき回しては平らに持つことを繰り返す。
「 伊勢は天照大御神…」とうたうときに、こりとりの際に汲んできた竹筒に入った浜水を釜に注ぎ入れる。
その後に、禰宜が「あら湯をば 森こそ静める あら湯をば」と唱えた後は、湯たぶさ で釜の湯をかき回し振り禰宜が釜を回る。
各々の湯立ての最後に舞上げを行うが、この大神宮の御湯の場合は大神宮柱に 向かって舞上げを行う。


大神宮の御湯のうたぐら
一 式なれば式ほど申す幾度も 幾度も御召し聞召し 給え御神
一 秋過ぎて冬の始めは今日かとよ 今日かとよ 風ものどかに やよい桜
一 峯は雪 ふもとはしぐれ里は雨 里は雨 雨にましたる あられなるらん
一 冬来れば渡る瀬ごとに氷橋 氷橋 金のくれ橋 かけや渡る
一 村雀育ちは何処(いずこ)よ伊勢の国 伊勢の国梅の梢で 育ちなるらん
一 宮川を皆(かい)連れ登る鮎の子が 鮎の子が鼻を揃えて御座と参る
一 千早振る天の岩戸を押し開き 押し開き神現れて 御行(げきや)召さるる
一 伊勢の国 参れば遠し来ぬれば 来ぬなれば 折りてたたみて 近く参る
一 伊勢の国 杉の村立を多ければ 多ければ 色ある杉が 栄えなるらん
一 伊勢の国 高天ヶ原の八重つつじ 八重つつじ 花の盛りで今日ほどめでたい
一 伊勢の国 高天ヶ原に立つ煙 立つ煙 ひわら古事記のにおいなるらん
一 熊野路のきりてが森のなぎの葉を なぎの葉を 嵐にかけて かけや渡る
一 熊野路の音無川のよどの瀬を よどの瀬を にごめてたつは鴨やおしどり
一 愛宕山おろす嵐が宵なれば 宵なればくれます宵が 久しかるらん
一 所では所の神がお召します お召します 神にかだされ ひめぐりのかわ
一 大社が森であなたこなたと呼ぶ声は 呼ぶ声は 大社が呼ぶか森が招くか
一 天照大御神のおり居の御座に今日ほど吉日綾をえて 錦を敷きて 御座と参る
一 天照大御神の湯殿へ降りし湯衣は 湯衣は たてが七尺 袖が六尺
一 湯の父は湯殿は何処とさし降る さし降る 下こそ湯殿よ 中は舞堂
一 かきたてる しでの葉ごとに降りる神 降りる神 神現れて 御行き(みゆき)召さるる
◎ 伊勢は天照大御神 豊受大神 降りいて花の玉の御刻(みこく
一 湯召すときの見るかげは 見るかげは湯元で見える かすみとぞなる
◎ 伊勢は天照大御神 内宮は八十末社 外宮は四十末社 浅間の山に諸々御神
天の岩戸に月日の御神 きりの御神 かすみの御神 成神様や星の御神 みる めの御神 祓戸御神 いちみこの御神 萬物御神
一 湯召すときの見るかげは 見るかげは湯元で見える かすみとぞなる
◎ 大神依りては八万八千の天津御神 地津御神 九万八千の天津御神 地津御神 高きは大神 低きは小神 諸々御神
一 湯召すときの見るかげは 見るかげは湯元で見える かすみとぞなる
一 神々の湯召すときの見るかげは 見るかげは湯元で見える かすみとぞなる
(禰宜)あら湯をば森こそ静める あら湯をば
(小禰宜)夜中の清水をこおりとる (二回繰り返す)
一 天照大御神の遊びする間に夜がほげる 夜がほげて 明けてつとめてどこを下る
一 何れ(いずれ)もわけて参らする 参らする 御召し 聞召し 給え御神
一 待ち待ちて御湯は今宵 さ夜中に さ夜中に 月待ち居たる 今宵なるらん
一 庭中に七つ釜立てわかす湯は わかす湯はそれさえ参れば 今日ほどめでたい
一 うれしげに 何をか取らせ花衣 花衣 高天ヶ原を ゆらりしゃらり
一 天照大御神を舞い上げるとの千早振る 千早振る どこにとどまる 神がやしろ
一 宮大神を舞い上げるとの千早振る 千早振る どこにとどまる 神がやしろ
一 祖々大神を舞い上げるとの千早振る 千早振る どこにとどまる 神がやしろ