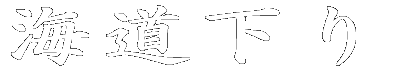
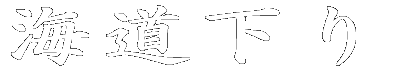
頬かぶりに袴姿で幣束と鈴を持った爺と、紋付きに橦木杖を持ち上衣を引きずり ながらヨロヨロと登場する婆が、湯釜を回ろうとすると、禰宜から「うったたれがないで通れん 」と紐を引かれて止められる。この後に婆が上衣をもち、
東方におんしたたれ
南方におんしたたれ
西方におんしたたれ
北方におんしたたれ
中央にお んしたたれと五方を拝む。
上衣を爺に着せて湯釜を回ろうとすると、さらに禰宜より「おんえぼしがないと通れん」と引き止められる。そこで禰宜より藁で作ったえぼしを受け取り、
東方におんえぼし
南方におんえぼし
西方におんえぼし
北方におんえぼし
中央におんえぼしと五方を拝む。
爺にえぼしをかぶせて釜を回ろうとするとまた禰宜より「 いんのこがないと通れん」とい われ、釜に付いたススを爺の顔に塗りつけられる。
やっと釜を回り禰宜から褒美にもらった大根をもち婆が五方を拝む。
大黒柱の前にて禰宜と爺婆で大根を餅に見立てて橦木杖にてつく。
この時、爺婆は禰宜のすねを、禰宜は爺婆のすねをつこうとして、餅をうまくつけない。
餅は一年12ヶ月より12回つく。
正月は年神の餅をつくつく餅をつく餅
二月は初午の餅をつくつく餅をつく餅
三月は雛の餅をつくつく餅をつく餅
四月は卯月の餅をつくつく餅をつく餅
五月は菖蒲の餅をつくつく餅をつく餅
六月は祇園の餅をつくつく餅をつく餅
七月は宝堂院の餅をつくつく餅をつく餅
八月は御射山の餅をつくつく餅をつく餅
九月は九日の餅をつくつく餅をつく餅
十月は恵比寿の餅をつくつく餅をつく餅
霜月は大司公の餅をつくつく餅をつく餅
師走はおとうの餅をつくつく餅をつく餅
師走の餅をついた後、幕の内に戻り海道下りが終わる。