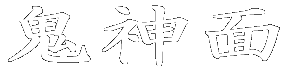
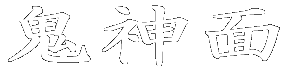
5日朝方6時頃登場する赤鬼で、船形の歯列ののぞく口に頬高の面で、笑ったように見えるのが特徴である。
この鬼は「笑っている鬼なので、皆を笑わせるように舞え」と伝えられている。
幕内より鬼神棒を持って登場すると、足を摺り寄せる動作をし「釜、大黒柱、楽頭様」の三方を三回づつ拝む。その後釜を遠回りして御殿に向かった後に禰宜と問答をする。
禰宜との問答にて位比べで負けた鬼神は鬼神棒を禰宜に取られ、右手に鈴、左手に扇をもって順の舞で五方を拝む。
鬼神棒を返してもらい三回舞うと天公鬼の登場となり背比べを行う。天公鬼が御殿に行き、三回舞うと退場となる。
(鬼神面の問答)
(禰宜)東西東西 東西とは静まれの言葉 そもそも伊勢天照大御神 東は浅間の神社 所の当社は氏大神 七石の神湯の十分沸き立つ所へ
逞しいきなりをして 踊り来る者は 何者に候
(鬼) そもそも伊勢天照大御神 東は浅間の神社 大阪より西も三十か国 大阪より東も三十三か国 合わせて六十六か国
東州は東海道とて 南州は南海道 東山道に山陰道 山陽道に西海道 北陸道とて道は七つに分けられて 舟道共に八つの御道
其内東国東山道へと指たる道の中定は 信濃は信州諏訪の郡 佐久の郡に埴科郡 更級郡に小県郡 水内郡の高井郡 安曇野郡に筑摩郡
伊那郡と領られたり 其内伊賀良の庄内関の郷 小名を取りては左閑邊と申す御所 七石の御湯は十分沸き立つとあり
吾は是諸神に仕え奉り 清め祓えと仰せに依りて 是迄も現れて 舞い降りたる 鬼きじんをとがめる者は何者だ
(禰宜)とがめる者はかたじけなくも伊勢渡会の国神(み)裳(も)裾(すそ)川(がわ)の流れにて 神の父 神の母禰宜博士がとがめる
(鬼) 禰宜博士がとがめる
(禰宜)それ程位高き鬼きじんなれば 位較べをしましょう
(鬼) 位較べをしましょう
(禰宜)神は十萬歳 仏は九萬歳 王は十二万歳の位を得給う者 鬼きじんは何萬歳の位を得給うや
(鬼) 事久しき鬼きじんの事なれば 鬼きじんは七萬歳 鬼きじんは七萬歳
(禰宜)七萬歳ならまだ三萬歳足らねによりて この神宝前を荒す事はなるまい 四方諸神を拝んで舞い還るが よかろう
(鬼) 左様なればこの神宝前は太夫のものよ この豊葦原国の北国は越後は越中 佐渡が島 物は食わでもひだるくはない
衣裳は着ねども寒くはない 年は寄りても顔にしわはよらぬ 福貴万福 栄華が島へと舞い還る
(鬼神の順の舞のはやし)
一 ありがたや誠が神行