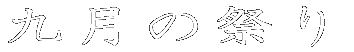
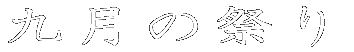
九月の祭りは、10月17日、18日に執り行われいる坂部の五度の祭りにおいては最も大きな祭りです。
17日には火の王社、諏訪社にて、18日には日代八坂神社において行われています。
各家において藁束を二つに折りまげ中にシロコモチ、又はゴクウを入れ、幣束をつけたテンゴンダカラを作ります。
祭りにはテンゴンダカラ、初詣りの際は徳利、十三歳で神子になる場合は新しい上衣、女の子の場合は酒を持って行きます。祭りに先立ち火の王社、日代八坂神社においては注連縄やタカラを切り替える祭花づくりをおこないます。
祭りは、禰宜様の祓詞から始まり 、御供を供えたのちに 祝詞奏上を行います。御供を御供えしている間に、天狗祭りを行います。
天狗祭りとは、テンゴンダカラを火の王社では舞殿隅の床下、諏訪社では御神木のとなりの天狗様、八坂神社においては西側の山の斜面にテンゴンダカラを供えるものです。
禰宜様の祝詞奏上が終わると注連引きを行います。この注連引きの最中、初詣りの子がいる場合はここで禰宜様と三三九度を交わし氏子にしてもらいます。
注連引きに引き続き、御供渡しのうたぐらをうたいます。
その後、順の舞(新宮人の舞)を四人で舞います。
この時十三歳で新しく神子になる子供がいる場合、禰宜様が新しい上衣を重ね着して舞うこととなっています。
次いで九月の祭りでしか舞われない市の舞が舞われます。
市の舞は本年氏子になった人数と亡くなった氏子の人数によっ て舞う回数を決める舞であり、
舞う回数=50−{(生まれた人の数×3)−(亡くなった人の数×3)} で決められます。
幣束と鈴を持ち、左回りから右回りにて一 回となり、次のうたぐらをうたいながら舞います。
「いち神子のさしでの顔は花かよ 花かよと 花にましたるめしょう神子」
市の舞が終わると次は順の舞(自分の舞)が舞われ、最後に禰宜様が舞上げをします。
舞上げが終わると、火の王様、水の王様に般若心経をあげ、お会いして祭事は終了します。
全ての祭事が終わると各祠に供えた赤飯やテンゴンダカラのゴクウを皆でわけ、直会をおこないます。同じ内容の祭事を各神社において行います。








