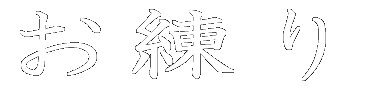
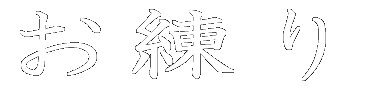
午後6時ごろ下の森、火の王社から笛、太鼓の祇園囃子に合わせて大森山諏訪社へと練っていく。
お練りは幣束を持つ補宜を先頭として御輿、浦安の舞姫、大太鼓。とりひげ、つるぎ、なぎなた持ち、太鼓多数、笛の順に列をなして諏訪社に向かう
お練りの一行が大森山諏訪社に到着すると同時に庭火がつけられて、以後観客らの暖となる。
神主と氏子総代や浦安の舞姫はまず、水屋で清めて、祓殿でお祓いを受けてから拝殿にのぼる。
拝殿にのばらない若者たちが神社の大庭で輪を作り、「伊勢音頭」と「願人踊り」を交互に三回ずつくり返す。(増える場合あり)伊勢音頭は大太鼓の打ち手がバチを持つ手を交互にかぎしながら腰を低く落とし、大きく跳ね上がって踊って輪の中をまわり一周すると舞殿におかれた大太鼓を二度叩く。これを三周くり返すと「願人踊り」となる。
「願人踊り」はとりひげを持ち、手拭をねじり鉢巻きにした願人(親父)が輪の中に出て、とりひげを上下させながら踊り、これと向かい合うように頼かぶりした女役が踊るものである。