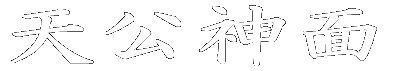
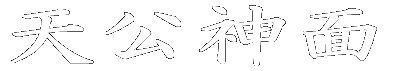
5日朝方6時過ぎに登場する赤鬼で、四角ばった顔にえらの張った面で、怒ったように見えるのが特徴である。
この鬼は「怒っている鬼なので、怒っているように舞え」と伝えられている。
幕内より撞木杖を持って登場すると、鬼神面と同様足を摺り寄せる動作をし「釜、大黒柱、楽頭様」の三方を三回づつ拝む。先に舞殿にて舞っている鬼神面と背比べをし、釜を遠回りして御殿に向かった後に鬼神面が退場すると禰宜と問答がはじまる。
禰宜との問答にて大暴れし位比べで負けた天公鬼はは撞木杖をを禰宜に取られ、右手に鈴、左手に扇をもってかやせかやせと五方を拝む。
撞木杖を返してもらい三回舞うと青公鬼の登場となり背比べを行う。青公鬼が御殿に行き、三回舞うと退場となる。
(天鬼公面の問答)
(禰宜) 東西東西 東西とは静まれの言葉 そもそも伊勢天照大御神 東は浅間の神社 所の 当社は氏大神 七石の御湯の十分沸き立つ所 へ 逞しいなりをして踊り来る者は何 者に候
(鬼) 吾々貴と申し候は 伊勢天照大御神 東は浅間の神社 天神七代地神五代 其末三十 代の後 天荒鬼王とは我が事 事の長さを申さ ば 九百九十九万九千と記し給えば 御湯が所望
吾は是諸神に仕え奉り 清め祓えとの仰せによりて 是迄も舞い降りた る 鬼天公鬼王をとがめる者は何者に候
(禰宜) とがめる者はかたじけなくも伊勢渡会の郡神裳裾川のほとりにて 神の父神の母禰宜博士がとがめる
(鬼) 禰宜博士がとがめるな
(禰宜)それほど位高き鬼天公鬼なれば 位較べをしましょう
(鬼) 位較べもよかろう
(禰宜) 神は十万歳 仏は九万歳 王は十二万の位を得給うや
(鬼) 事久しき鬼天公鬼王の事なれば 天公鬼王は七万歳
(禰宜) 七万歳なら未だ三万歳足らねによりて この神宝前を荒すことはならぬにより その引き杖を太夫に御渡し
(鬼) この七つの由緒のある杖を太夫に渡してなるものか
(禰宜) 由緒を聞きましょう
(鬼) 由緒を聞きたければ話して聴かせる 昔 東方○天竺よりこの豊葦原の国へ伐りとばせられたる時の桑の木の本へと立ち 寄り て 本の切株金剛杖 末の切口胎蔵杖 向う三尺一寸一分にきりとばせられたる 時の桑の木の杖 神に金剛杖 仏に座禅の杖 人間 に力杖とて 此の七つの謂われの ある杖を滅多無性に太夫に渡してなるものか
(禰宜) 謂われは聞いたが その引き杖を禰宜があずかる とがめる者はかたじけなくも伊勢渡会の郡神裳裾川のほとりにて 神の父神 の母がとがめる
天公鬼のはやし 一 かやせ かやせ 清めてかやせ